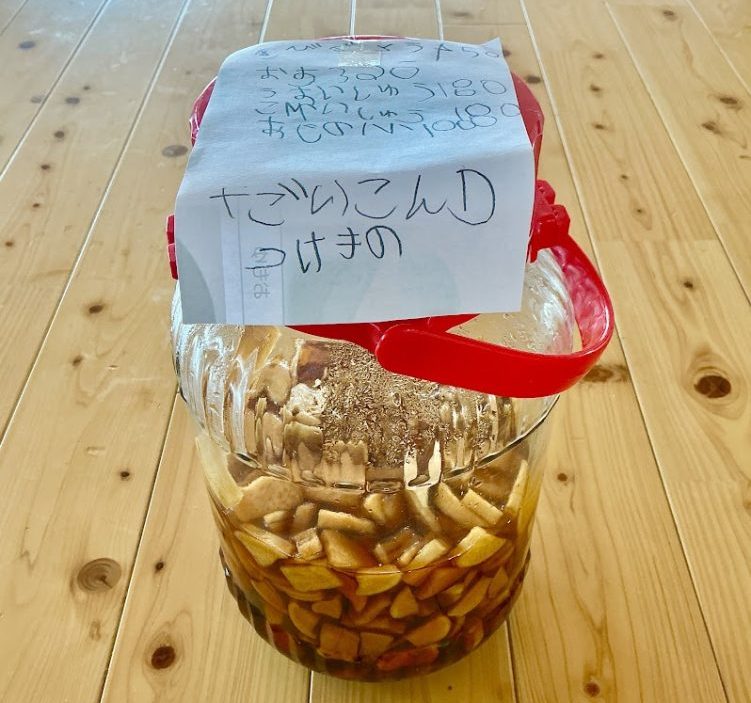お知らせ
2025.10.23
Blog
自然から学ぶ保育教育(園庭担当)

秋らしい爽やかな風が心地よい季節となりました。
当園自慢の園庭やビオトープも次第に秋らしい姿を見せ、毎日子どもたちがどんぐりや落ち葉を探したり、赤とんぼやバッタ、コオロギを見つけて観察したりと、遊びが様々に広がっています。
今年度は、橋口創也さんを理事に迎え、より人と自然が調和する心地よい園庭作りを目指して改革が進んでいます。
先月、橋口さんを講師にお招きし、現在の園庭の環境やこれから目指していく園庭の姿についての職員研修を実施しました。今回は、その研修から得た学びについて紹介したいと思います。
土が元気になることで生まれる循環
1学期時点では、園庭の傾斜から雨水が勢いよく流れることで、土壌を豊かにするための微生物が泥水とともに流れてしまっていました。
雨水の通り道の新設、各所にウッドチップを蒔き、土壌に栄養を与えるなど、地道な工夫を重ねることで、現在は新しく雑草が生えてきたり、花が咲いてきたりと、緑が多くなってきました。
橋口さんのお話によると、雑草が生えることで植物が地中に根をはり、根の部分に土壌を元気にするための微生物が住みやすくなるそうです。
少しずつ園庭の環境がより良い状態に近づいてきたのだな、と嬉しく感じました。
・土が元気になる
・多様な草花が生える
・様々な虫がやってくる
・虫たちが花粉を運ぶ
・他の生き物との共生が起こり、また新たな食物連鎖や植物が育つ
このサイクルが整えば、子どもたちにとっても様々な植物や生き物と触れ合う機会が増え、さらに自然を生かした学びへと繋がるのでは、と期待が膨らみます。
自然環境と教育環境の共通点
教育に携わる人間として、研修の中で興味深いと感じたテーマは、「自然環境における多様性」についてでした。
自然環境の中では、「弱肉強食」と言われるように、強いものが勝つ、というイメージが強かったのですが、この研修では、「自然界では、その環境下で他の動植物と共生できるものが生き残る」ということを学びました。
弱っている植物に対し、元気な植物が土を介して栄養を分けるということが、豊かな自然の中では存在するそうです。
私たちが行なっている保育も同じで、
集団生活の場面でも、力の強いものが勝ち残るのではなく、互いに助け合い気遣いあう中で、しなやかに集団の中で生きていく力を育てていきたいと感じます。
そのためには、自然界でいうところの土壌の役割を保育者が担い、豊かな環境と温かなまなざしのもと、困っている人、足りない何かについて子どもたちに気づきを与えるような働きかけを行っていく必要がある、と改めて考えることができました。
この半年の取り組みにより、園庭には小さな生き物がたくさん増えました。
優しく触らなければ死んでしまうことや、生き物の餌となる植物はすぐに再生するわけではないことを、子どもたちは体験を通して学んでいる最中です。
園庭がより豊かになることで、動植物が増え、子どもたちが自分とは異なる、小さな命、物言わぬ命について気付き、思いを巡らせることが増えてくるのでは、と期待しています。
これからますます変化を続ける園庭に、ぜひお子様とお立ち寄りください。
文責:津田