お知らせ
2021.02.09
Blog
子どもの「手づかみ食べ」はなぜ良いのか?・・・本の紹介

子どもの「手づかみ食べ」はなぜ良いのか?
この題名の本をご存じでしょうか?
読み始めると、子育て中のお父さんお母さんたちなら、「それそれ」「わかる~」と頷きながら読むところがたくさんあると思います。
そして、「手づかみ食べがそんなことと関係があるの!?」と不思議に思うこともでてくると思います。
今回は、そのような学びいっぱいの本、『子どもの「手づかみ食べ」はなぜ良いのか?』について、ご紹介いたします。

「自分で食べたい!」から自己肯定感を育てることにつながる、手づかみ食べ
「手づかみ食べ」は子どもの意欲を引き出し、手指などの機能も向上させます。そして、やがてくる自立心を育てていくためにも大切だとあります。
では、「手づかみ食べ」と子どもの意欲、どんな関係があるのでしょう?
食べるということは、命を保つこと、命を守り育てることです。その自分の命を守る「食べる」という活動を「自分でやるんだ!」という第1歩が手づかみ食べです。
手づかみ食べは、自我が成長していくうえでも非常に大切です。
しかし、初めて「自分で!」という意識が生まれ、自我や意欲が育っていくこの時期に「それはダメ!」「やめて。散らかるでしょ!」(そう言ってしまう気持ちはよくわかります。私も私も我が子の時、汚したくない思いから新聞紙を敷いていました)と言われていると、子どもはいつも「自分」を否定されていることになります。
すると、そのような言葉掛けを繰り返された子どもは、自分に自信のない子、自分のやることに価値を見出せない子になってしまいます。お母さんはただきれいに食べさせたいと思っているだけなのでしょうが、図らずも子どもには自分を否定するメッセージになってしまっているようです。
そうやって、手づかみ食べを否定していると発達のうえでどんな問題がでてくるのでしょう?
自分に自信がないと、日常的な遊びや生活においても、自主性や主体性に欠ける子になるそうです。1歳を過ぎても自分で食べるより、大人が差し出す物を「あーん」と口を開けて食べてきた子に多くみられる行為です。
手の指は「突き出た大脳」
手の指は「突き出た大脳」と言われるくらい脳の発達に大切な部分です。
その指を使って食べ物を食べるという事は、知的な発達に繋がります。時期が来ればこぼさないで食べられるようになりますから、あまり発達を焦らずにじっくり待っていいそうです。
また、食べ物を手のひらでぐしゃぐしゃに握りつぶす時期がありますね。この経験が感覚を受け入れる器を広げ、そこで経験する感触が土や泥を嫌がらずに触れる子どもを育てていくそうです。
食べることが、子どもの脳や性格、行動の形成にどのように関係していくのか、子どもの成長を考える上で、とても勉強になります。
この本の後半部分には、赤ちゃんだけでなく、少し大きくなった子どもたちにも関係のある朝ご飯のことや、「早寝早起き朝ご飯」改め「早起き早寝朝ご飯」など、乳幼児期を過ぎていてもかわいい子どもたちの為になるヒントがたくさん書かれています。
ご自分の関心あるところからでも読んでみませんか?
【参考】
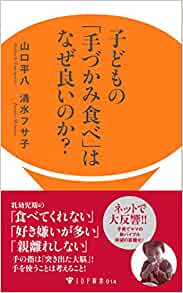
文責:福元 恵美子






