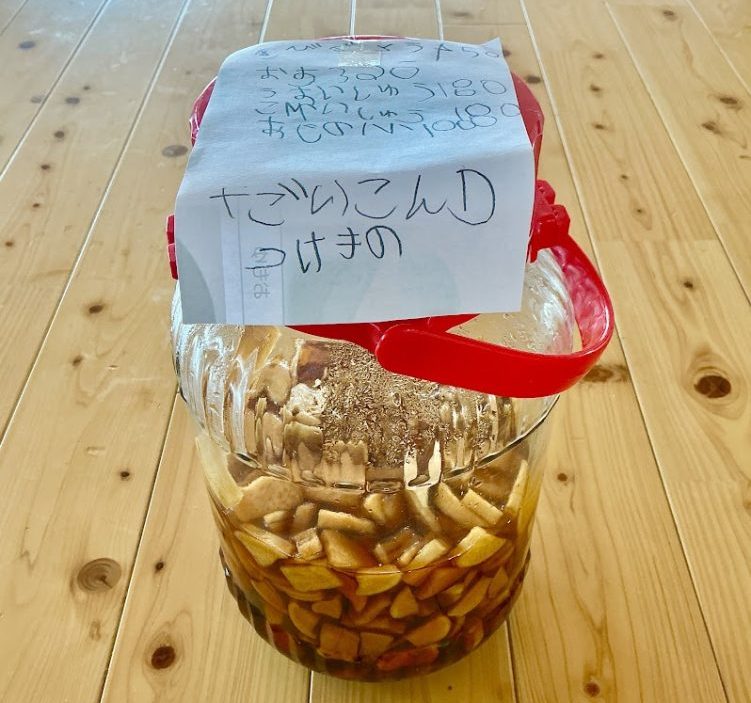お知らせ
2022.11.25
Blog
当たり前を見直す

先日、年長(5歳児)そら組の子どもたちと遊んでいる時、ある「ルール」が話題になりました。
その日は、男の子8人ぐらいと私でLEGOで遊んでいました。
石油タンカーを作りたかった私は、LEGOをごそっと取りました。すると、その場にいたから子たちから、「ずるい〜!!」の一声がかかりました。
私「え?なんで?何がずるいの?」
A 「一人でそんなにいっぱい(と言っても、私が取ったのは20個ぐらい、目の前のLEGOは何百ピースもあります)取ったら、他の人が足りなくなるじゃん?」
私「こんなにたくさんあるのに?一つずつなんか取ってたら、いつまでも完成しないじゃない?」
「みんなはどう思ってるの?このルールのこと。私は、何だか、変なルールだと思うけど…」
みんな「うーん…」
私「このルール、どんなふうに決めたの?」
みんな「大人…が、決めた」
私「分かった、このルールのことと、みんなの気持ち。年長の大人に伝えとくね」
といった会話がありました。
ルールは必要だという意見と、大人が言うから守っているという意見。子ども達の言葉からそんな印象を受けた私は、その後、先の会話を年長の大人に伝えました。
すると、「そんなルール、決めてないですねぇ…」と、苦笑い&困惑の大人二人。
やはり…
私の直感は当たっていました。
普段から対話を大切に、子ども達の思いを尊重した保育を心掛けていることを思うと、大人が子どもの行動を制限するようなルールを作るかな?と、そう思ったのでした。
子どもたちにこの結果を伝えるために、再びそら組へ向かいました。
聞かせて、みんなの意見
この出来事から、「日頃から子ども達が思っていることを聞き出してみよう」と思い立ち、そら組のサークルタイムに参加することにしました。
まず、年長組大人二人の話を伝えると、子ども達は「これまでは何だったの?」と言いたげに、唖然茫然。
そこから、「この他にもこうして欲しい!」と思うことをどんどん教えて欲しい!と、子ども達に言葉を投げかけました。最初は、LEGOにまつわることばかりでしたが、子ども達の言葉を否定せず、「なるほどそうか、分かった。じゃあ、他のことがある?」という言葉を繰り返しかけ続けました。
すると、「給食の(準備の)時、並ぶのが嫌だ!」という意見が出ました。
詳しく掘り下げて聞いてみると、「ご飯を、炊飯ジャーからつぐときに長い列ができる。早く食べたいのに、食べられないから困っている」という内容で、クラスの約半数の子ども達が同じ意見を持っていることがわかりました。(この案は、すぐに子ども体により対策が立てられて、子どもたち曰く、楽になったということです☆彡)
次に出てきたのは、
「帽子を取りに行くのがめんどくさい、今、カバン棚のかごの中に置いてあるが取りに行くの大変なので、もっと取りやすいところに帽子を置くようにして欲しい」
「フェスタのことをする日が嫌だ…」
などなど、様々な意見・思いが出てきました。
子どもたちの声を聞くことで改めて、子どもたちは大人が思ってる以上に色んなことを考えていて、思っている。子どもって素敵、素晴らしい!と思うことでした。
面白楽しくも、色んな発見があり、何とも言えない素敵な時間でした。
自分事として考える
今回の話し合いでは、
〇園の生活を自分事として考えてみる
〇自分の思いに気づく
〇思いを自分なりの言葉で伝えてみる を活動のねらいとして取り組みました。
これらのねらいを達成するために、私自身が大切にした3つの言葉がありました。
1.どうしたの?
→ ご飯の時並ぶのが嫌だ (考えの整理)
2.みんなはどうしたいの?
→ 並ぶ時間を短くしたい (意思確認)
3.何かできることある?/みんなはどうしたい?
→ ご飯を二つに分けるようにして欲しい!
→ OK!給食室に相談してみよう! (問題解決の手助け)
この3つの言葉を軸にしたやり取りで、子どもたちの考えを整理、意思確認、問題解決の手助けのプロセスを経ることができます。
実際、この言葉のやり取りの中で、自分たちのことを自分たちで決めることができました。そして、子どもの中には、「自分たちで色々決めることで、こども園はもっと楽しいところになるかもしれない!」という気付きを得た子もいたかもしれません。
また、当事者意識の芽生えも促すこともできます。
いろんな考えが頭の中を巡り、子どもたちになりに言葉にしたものを大切に受け止めてもらうことで、「心理的安全性」が高まったり、会話が生まれたり、社会性が育まれたりしていきます。このような経験を通して、日常がもっと豊かなものになっていくのだと思います。
このような、子どもの声に耳を傾ける会話は、こども園の日常に溢れています。運動会もフェスタも、毎日の生活も、このような会話がベースです。大人が作った覚えのないルールの話を聞いて困惑していた年長の職員も、「立ち止まった子どもの言葉に耳を傾けることを、もっとやってみたい!」と意気込んでいます。
子どもと大人は立場は対等。ちょっと立ち止まって、「子どもの心」に耳を傾ける感覚で、双方向のやり取りを行っています。
もっと素敵なこども園になっていきそうな予感です…!
この活動の最後に、私から子どもたちにこのように伝えました。
「こども園の大人は、みんなのことを思って色々決めてたりお願いすることもあると思うの。みんなのことを大事に思ってそうしたことも、みんなにとってはいやだと思うこともあるかもしれない。今日のLEGOのように、みんなから『これは困る』ということをこれからもどんどん教えて欲しい。こども園は皆のもの。もっと楽しい園にしたいです。」
その後…
サークルタイムの中で出た、LEGO以外の2つの意見。それぞれ検討が進んでいるようです。
○帽子について
タオル掛けに帽子をかけてみてはどうか?の意見が出てるようですが、タオルもかかっているのでこれでいいか?と話し合いの途中だそうです。
○フェスタについて
意見を言ってくれた子へ、もう一度フェスタについて話を聞いたそうです。
するとその子は、『一度決めたグループ以外は、「やりたいな!」と思っても変更はできない』と、勘違いしていることが分かったとのこと。改めて、「フェスタは自分がしたいことをするんだよ!」ということと、「一つのグループに限らず色んなグループに行って、自分のしたい!を見つけていいよ!」と伝えた後は、いろんな事に挑戦し、いきいき活動しているそうです。
今後も、このようなやり取りは毎日続きます。
子ども達一人一人が主役の園。誰にとっても居心地のいい園であるために、大切な時間として私たちは捉え、取り組んでいきます。
参考文献:「最新の脳研究でわかった!自立する子の育て方」工藤勇一・青砥瑞人(SB新書)
文責:後藤