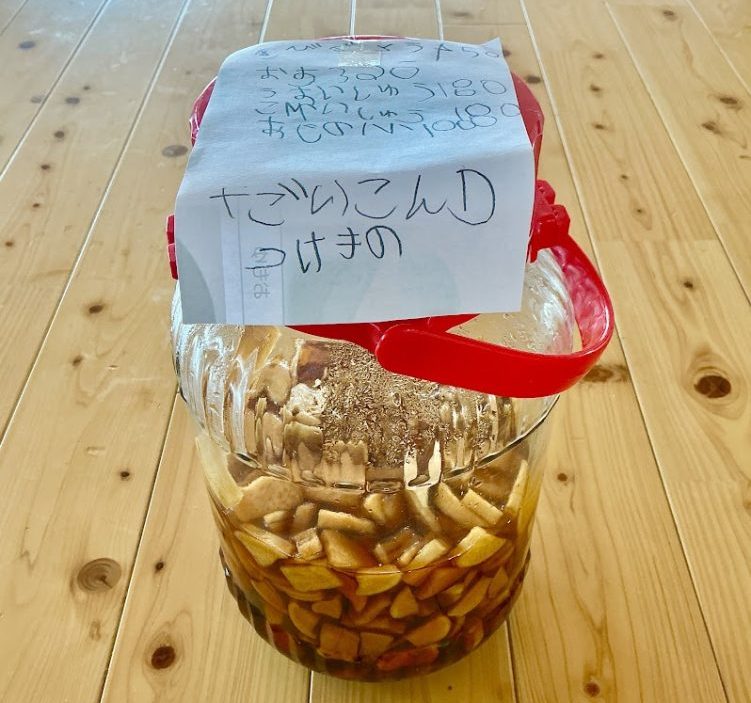お知らせ
2023.02.14
Blog
わらべうた 〜お手玉編〜 (4歳児 年中組)

年中組1月のブログでお伝えしましたが、「昔遊び」まだまだ続いています。
その中でも、最近夢中になっているのがお手玉を使ったわらべうたです。
私も、小さい頃お手玉で遊んだ思い出があります。祖母が、3つのお手玉を左右の手で交互に投げながらわらべうたを唄っていたました。私も真似てやってみましたが、二つはできても、三つはできずに何度も挑戦しました。結局、できるようにはなりませんでしたが…。
お手玉遊びで育つこと
誰でも気軽に楽しめるお手玉遊びですが、その遊び方にたくさんの魅力が隠されています。
☆脳を刺激することでさまざまな効果が期待できる
色鮮やかな見た目から視覚、手に持って遊ぶことから触覚、中身の音が鳴ることから聴覚がそれぞれ刺激され、脳の活性化に繋がることで集中力が高まると言われています。
☆リズム感やバランス感が養える
お手玉で上手に遊ぶには全身を使ってリズムをとることが重要だそうです。歌を歌いながら遊ぶとリズム感の向上が期待できます。また、片手で投げて片手でキャッチするという動作は意外に難しく、バランス感を養うこともできます。リズム感やバランス感は子どもの成長に欠かせない大切な要素です。遊びの中でこれらが養えるというのは嬉しいですね。
☆複数人でも楽しめる
ひとりでも、複数人でも楽しむことができるお手玉遊び。友達や親子で向かい合って「せーの」で投げっこをしたり、輪になって歌を歌いながらお手玉を回したり、遊び方は無限大です!
☆赤ちゃんから大人まで長い期間楽しめる
産まれたばかりの赤ちゃんははにぎにぎ遊び、1歳前後になったら「どうぞ」、「ありがとう」のごっこ遊び、大きくなったら本来のお手玉遊び。
お手玉は老若男女問わず長い期間楽しめる遊びです。
※たくさん遊んでいると、稀に糸がほつれて中身が出てきてしまうことがあります。赤ちゃんの誤飲に繋がる可能性があるので、メンテナンスはしっかり行いましょう。
お手玉で遊んでみよう!
「これ、何か知っている?」の問いかけに、数名の子どもたちが、「お手玉!」と答えてくれました。
一つずつ渡すと、早速、ぎゅっと握りしめたり、ポーンと上に投げてみたり、「かわいい花だね」「中に何が入っているのかな」と呟いたりしながら、触覚・視覚・聴覚などの五感に刺激を感じて遊んでいましたよ。
今回は、二つの遊びを紹介します。
♪おじぞうさん こんにちは♪
「お地蔵さん」でお手玉を自分の頭の上にのせ、「こんにちは」で頭を下げ、落ちてきたお手玉を手で取ります。
簡単なようで、油断すると取ることができません。子どもたちは、夢中になって何回も繰り返して遊び、どこに落ちてくるかわからないドキドキ感に夢中になっています。


♪あんたがたどこさ♪
①一人遊び~歌に合わせて両手で上に跳ね上げる
力が強すぎて遠くに飛んでしまったり、落とさないようにそっと跳ね上げたりと、試行錯誤していました。慣れてくると「できた!」と嬉しそうに何度も遊んでいましたよ。
②二人遊び~歌詞の「さ」の所で相手に渡す
「さ」のタイミングに合わせるのが大変でしたが、歌をうたいながら「さ」の時をドキドキしながら待っていましたよ。
友達と『息を合わせる』『心を合わせる』ことがコツになります。いつのまにか、自然に目と目を合わせて息がピッタリとあってきました‼
③集団遊び~輪になって、歌詞の「さ」の所で次の人に渡す
歌をうたいながら、お手玉の動きを目で追っています。「さ」のタイミングになると、自分の番ではない子どもまで一緒に体を揺らし、みんなの心が一つになっているように感じました。

他にも『おてぶしてぶし』や『せんべいやけた』『さよならあんころもち』など、まだまだたくさんの遊びがあります。
遊びを通して、友達と触れ合い、一体感を感じられる遊びって素敵ですよね。
これからもたくさん遊んでいきたいと思います。ぜひ、ご家庭でも遊んでみてくださいね。
文責:川宿田
参考文献:https://hugkum.sho.jp/99104