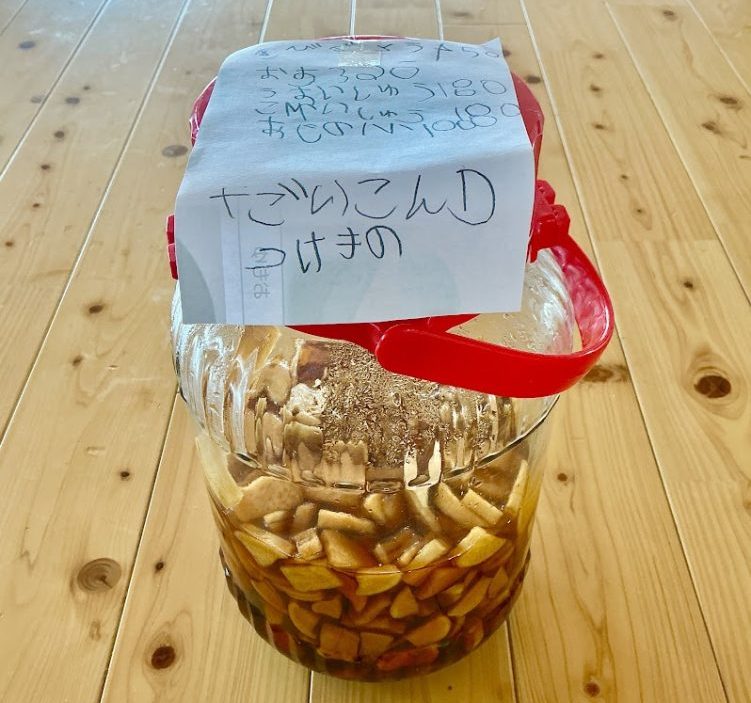お知らせ
2022.09.03
Blog
年中・年長だより ~2学期がはじまりました~

夏休みが終わりましたね。
園では、久しぶり登園した子ども達から楽しそうな声がきかれ、安堵のスタートとなりました。
ちょっと前を振り返りますが、1学期はいかがでしたか?
4月に入園されたご家庭、保護者の方が仕事復帰されたご家庭等、さまざまな環境の変化があり、生活のペースを整えることが大変だったのではないでしょうか。
今回のブログでは、遅くなりましたが、年中・年長の「1学期の振り返りと2学期に向けて取り組みたいこと」をお伝えします。
ご家庭でもぜひ、1学期のできるようになったこと等を振り返り、2学期からこうしていけたらいいね!と、親子でそれぞれの思いを伝え合い、話し合う時間を設けていただけたらと思います。

〇1学期の振り返り
年中組、年長組それぞれ、集団生活の中で次のようなことができるようになってきています。

〇 年中組(4歳児)
1 園生活に見通しをもって過ごすことができるようになってきています。 → 自立心につながります。
子ども達の園生活は、おおまかに【登園 ⇒ 歯ブラシセットやタオルの準備等 ⇒ 午前の活動 ⇒ 給食 ⇒ 歯磨き・着替え ⇒ 降園または午睡 ⇒ 午後の活動 ⇒ 帰る準備 ⇒降園】という活動・流れをたどります。
これらの活動を、ある程度の時間で、保育者の援助なく自分達でできるようになってきています。凄いですね。
ちょっと時間を要するお子さんや自分の物の管理が難しいお子さんは、保育者が声をかけ、自分でできるよう見守ったり、お手伝いしたりすることで、自分で取り組むことができています。
2 大人の話を身体や目を向けて聞けるようになってきています。→ 言葉による伝え合いを楽しむ力につながります。
子ども達自身が”話をきくことは大切だ”と感じ始めており、「大事なこと話すよ!」「これからどうするかお話しするよ」と言うと、身体や目を保育者に向けて話を聞けるようになってきています。
保育者が話をしている時に子どもが発言することに対しては、「今は聞く時間だよ」「誰がお話しする時間?」などの声掛けをすることで、子ども達自身が考えて工夫することができています。この経験を重ね、話をきく時の簡単なルール作りができてきています。
また、話を聞きそびれた子どもは、保育者に『次はどうすればいいかわかりません。』『困っています。』と伝えることも大切です。困ったときに受け身ではなく、自分で考え、工夫する力が育ちます。
このような経験も通して、繰り返し話を聞くことの大切さを伝えていきたいです。
3 さまざまなことや物に興味を持ち、深めようとし始めています。→思考力の芽生えにつながります。
生き物、食べ物、自然、乗り物、テレビ番組、本、音楽、ダンス等、子どもによって興味は様々です。
①言葉の理解や語彙力が高まり、②目で見たことに興味を持つ力の高まりから、いろんなことを自分なりに考えたり、調べたり、知りたいと思っている様子がみられます。
考えたこと、気付いたこと、知ったことは、自分の宝になりますね。
4 言葉で伝えようとし始めています。→言葉による伝え合いを楽しむことにつながります。
少しずつですが、園での様子をご家庭で話そうとする姿がありませんか?
文章がつながらなかったり、何を言っているか分からなかったりすることもありますが、子ども達は一生懸命、何かを伝えようとしています。
この時、大人が目を見ずに何かの片手間で聞く態度を続けていると、子どもも「話を聞くということは、そういうことだ」と認識してしまいます。
自分の周りの大人に伝えたいという欲求がある今、大人の聞く姿勢がポイントです!
言葉で伝えようとするこの時期、私達大人がしっかり目を見て聞いて、伝えたことを聞いてもらえたという満足感を子ども達が感じることが、さらに「伝えたい!」という思いに繋がります。
5 人との関係性が出来始めています。→言葉の伝え合い、社会生活との関わり、道徳性・規範意識の芽生えにつながります。
ご家庭で園のことを話すとき、お友達の名前がでてきませんか?
少しずつ友達と一緒に遊ぶことが楽しくなってきたり、言葉での感情のぶつけ合いが始まったりしてきます。
「○○さんが嫌なことをする」「○○さんと○○して遊んだ」など、人との関わりの中で自分と人との思いや考えが違うことを、少しずつ感じ始める時期です。

〇 年長組(5歳児)
1 園生活を見通しをもって過ごし、自分の身辺整理ができるようになってきています。→ 自立心につながります。
【登園 ⇒ 歯ブラシセットやタオルの準備等 ⇒ 午前の活動 ⇒ 給食 ⇒ 歯磨き・着替え ⇒ 降園または午睡 ⇒ 午後の活動 ⇒ 帰る準備 ⇒ 降園】という、園生活の流れ・活動でにおいて、自分たちで時間を意識し、短い時間で準備ができるようになってきています。
また、忘れ物をした時は自分から大人に「忘れた」と伝える事ができたり、思うように進まないことがあっても気持ちを切り替えて次の活動に参加できたりすることができています。
2 大人の話を聞いて、聞いたことを自分達の行動に移すことができるようになっています。→道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わりにつながります。
聞いたことを理解し、自分達で考えて行動に移すことができるようになってきました。
また、話を聞いた上で自分なりに考えて、自分の意見を持ったりできるようにもなっています。
3 いろいろな知識が増え、さらにその知識を深めようとしています。また、自分の好きなこと、得意なことが分かり始めています。
→思考力の芽生え、自然との関わり・生命尊重、数量・図形、文字などへの関心・感覚の高まりにつながります。
図鑑、辞典が好き!という子どもも増えてきています。本だけでなく、いろいろなことから知識を増やし、興味が深まっていくといいですね。
子ども達の様子を見ているとついつい大人は「もっと○○にも興味を持ってほしい…」と思ってしまいますが、大人は自分の価値感で判断するのではなく、子ども自身がもった興味に「いいねぇ~!」「いいじゃない!」と声をかけてみてください。
4 友だち同士の会話が増え、自分の考えや思いを伝えるだけでなく、相手の考えや思いを聞くことをし始めています。→言葉による伝え合い、協同性、思考力の芽生えの高まりにつながります。
5 グルーブ活動の中で、グループ名や係を決めたり、グループで出た意見を1つにまとめたりすることをし始めています。→協同性、社会生活との関わり、思考力の芽生え、言葉による伝え合いにつながります。
話し合って1つに意見をまとめるって難しいですよね。
子ども達も自分の意見を大切にしながら、そして悩みながら、頭の中がいろんな思いでグルグルなっているのだと思います。

〇 2学期スタートしました。
いよいよ2学期がはじまりました。
次の3点を少し意識して生活を過ごしてみてください。
〇園でしたことや感じたこと、思ったことを聞いてみてください。
→「園で○○して遊びたいなぁ。」「○○ちゃんと○○したことが楽しかった。」「○○さん(保育士)と遊びたいなぁ」という気持ちを引き出すきっかけになります。
言葉での伝え合いを特に大切に、子どもの思ったことや考えたことを引き出して、「そう思ったんだね。」「そんなふうに考えたんだね。」「上手にお話できるようになったね。」「お話とってもわかりやすかったよ。」と声をかけてみてください。
「もっと伝えたい!」という意欲に繋がります。
〇生活リズムを整える。
→園生活の活動を安心して過ごせる体調を整えることにつながります。
起床就寝時刻、食事のペース、おやつの取り方、身辺処理(手洗い、着替え、はみがき等)を、徐々に通園に合わせて調整していきましょう。
〇登園の準備(着替えや持ち物)を自分でする。
→園生活を思い出し、自分のことを自分でしようとする気持ちや2学期○○しようという気持ちを高めるきっかけになります。
登園の準備をする際は、着替え、帽子、水筒、ハンカチなど、自分の衣服や持ち物の準備を自分でやってみる機会をつくっていきましょう。
特に年長組は、就学に向けて、『自分のことは自分で』という土台をつくっていきたいですね。
子どもの会話の中で「○○くんと遊んだ!」「~が楽しかった」等の良いことを聞くと大人は安心しますよね。
一方、「嫌だった」「叩かれた」「仲間に入れてくれなかった」等の言葉を聞くといじめられているのではないか、お友達と楽しく遊べていないのではないかと心配になるのではないでしょうか。
子どものことで何か心配なこと、わたしたち保育士がわかっているかな?知っているかな?と思う事がありましたら、ぜひ私達にも教えてください。
送迎時の際でもいいですし、連絡帳などで希望日時(例えば降園時刻30分前)などを教えていただけると、お話する時間を設けます。遠慮なくお申し出ください。
文責:壽福