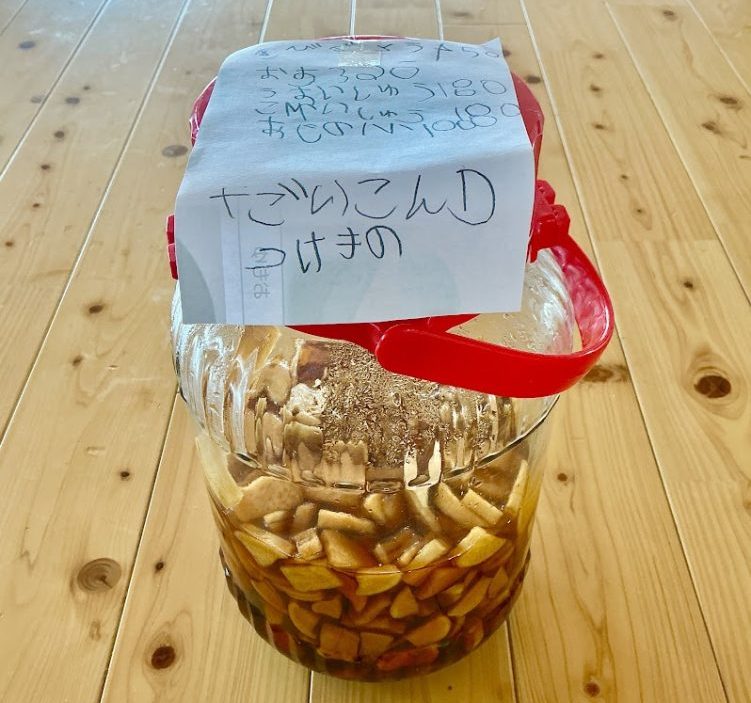お知らせ
2022.11.18
Blog
錦ヶ丘の表現とは①~保育を通して育てたい力~

今年度も12月に、にしきっこフェスタを予定しています。それに伴い、「子どもの表現とは何か?」について、夏の終わりに職員研修を行い、学びを深めました。
研修を通して、従来の発表会からにしきっこフェスタになった経緯や表現の捉え方、大切にしたい事等の表現活動の方向性を合わせることができました。
なぜ「発表会」から「にしきっこフェスタ」になったの?
5年前までは、保護者の皆様が幼い時に経験されてきたような、手作りの揃いの衣装を身に付けて、ステージに立ち、遊戯や劇、歌、合奏を披露する「発表会」がありました。
遊ぶ時間を削り、繰り返し練習に取り組むことで「上手にできた!」という当日の達成感があったのを覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その頃の保育は、自分のやりたいことをやり込むというよりも、保育者の指示を聞いて一斉に活動する保育が主流でした。
錦ヶ丘でも、以前はそのような形の保育・お遊戯会を行っていましたが、2018年の幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改定されたことをきっかけに、これまで当たり前にやってきた保育や行事等の見直しました。
これからの保育で求められる力は?
これからの目まぐるしい社会の変化の中を生きる子ども達には、「何を知っているか」という知識よりも、得た知識や技能を使ってどのようによりよく生きるかを考える力が求められています。
その力は、自分で考え試行錯誤しながら粘り強く生きていく力や好奇心、気持ちを切り替える力等の「非認知能力」です。
今回は、非認知能力について理解を深めていきたいと思います。
非認知能力って何だろう?
人間の能力は、「認知能力」と「非認知能力」の2種類に分けられます。
「認知能力」・・・・IQ(知能指数)やテスト等の点数等で数値化できる知的能力のことです。
「非認知能力」・・・認知能力以外の能力を示す言葉で、テストなどで数値化することが難しい内面的なスキルのことです。

非認知能力の種類
①自己認識…やり抜く力、自分を信じる力、自己肯定感
②意欲…学習志向、やる気、集中力
③忍耐力…粘り強く頑張る力
④セルフコントロール…自制心、理性、精神力
⑤ メタ認知…客観的思考力、判断力、行動力
⑥社会的能力…リーダーシップ、協調性、思いやり
⑦対応力…応用性、楽観性、失敗から学ぶ力
⑧クリエイティビティ…創造力、工夫する力
このように、非認知能力は社会への対応力であり、人生をより豊かにするための生きる力になるのです。是非、身につけたい力ですね。

非認知能力を伸ばすには、遊びを通じた学び(アクティブラーニング)がポイントになります。
自分から興味のある環境に関わることで、「自分で考える力」や「試行錯誤しながら工夫する力」をつけ、高めていきます。
このように、これから求められる非認知能力を育てていくには、日常の遊びがとても大事になってきます。
ですので、にしきっこフェスタに向けても、日常の遊びをじっくりと取り組みながら、子ども達の当日までの過程を大切に進めていきます。
日常の遊びの中で、子どもが学び、気づき、工夫してきた過程を表現と捉え可視化し、ご家庭と共にお子様の成長を共有できる機会をにしきっこフェスタとして開催しています。
表現の捉え方や大事にしている事、テーマ等についても、これからのブログでお伝えしていきますので、是非ご一読ください。
参考・引用:https://www.lacicu.co.jp/blog/category/management/learning/p1752/
文責:山﨑