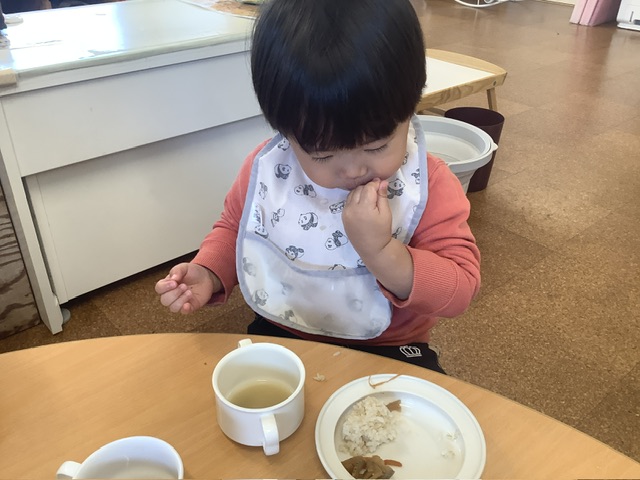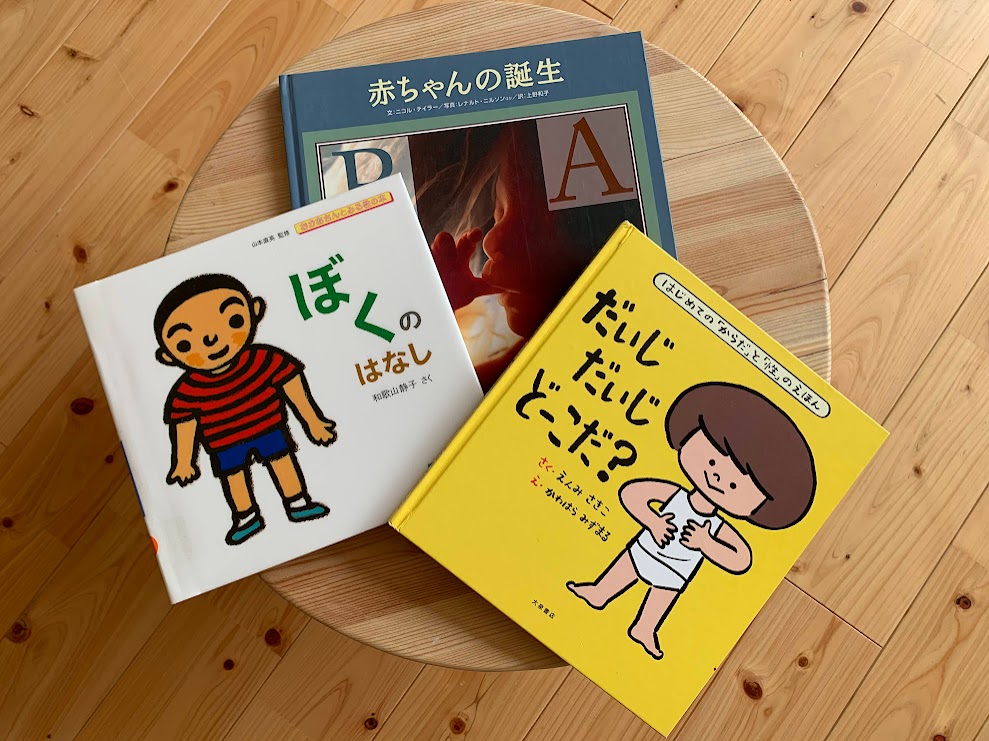お知らせ
2022.05.24
未分類
運動会にむけて③~かけっこ編~

いよいよ今月に迫った運動会、年長では全員が参加する「つなひき」とは別に、選択競技として「かけっこ」を行う予定です。
今年は子どもたちとの話合いの結果、「ストライダーかけっこ」、「なわとびかけっこ」「走ってかけっこ」の3つを子どもたちが自由に選んで参加することになりました。
園生活最後の運動会

認定こども園錦ヶ丘の運動会が他とちょっと違うところは、運動会で行う競技を決める際、大人がほとんど介入しないところにあります。
子どもたちが自分でやりたいことを考え、相談しながら作り上げていきます。大人は子どもたちの意見を取りまとめたり、自分の思いを発信することが苦手な子がいれば少し援助したりと、ほんの少しだけお手伝いをさせてもらっています。
5歳から6歳では、
・人との違いがわかり、自分と違うところも大切にできるようになる
・自分の意見が通らない場面でも折り合いをつけられるようになる
・「ことば」の大切さに気付き、話合いで色々な問題を解決しようとする
という社会性が育つ大切な時期に差し掛かります。
意見を伝え合い、みんなで一つのものを作り上げていく楽しさと、反対にうまく伝わらないときのもどかしさを感じながら、子どもたちが同じテーマに向かって考え、話し合っていく過程を錦ヶ丘では大切に考えています。
大人が運動会のプログラムを考えてあげたほうが効率は良いですし、楽な面もたくさんありますが、今の発達段階だからこそできることを最大限に生かしたい!
そう考え、こういったオリジナリティのある運動会を企画しています。
「かけっこをやる」「やらない」の背景にあるもの

どちらも大切な意思表示
「かけっこ」は、子どもたちの「やりたい!」という意見が多くあり組み込まれたものですが、「やりたくない」という意見ももちろんありました。
ついつい「やりたくない」を消極的な言葉としてとらえて「でも、がんばろうよ!」と励ましたくなってしまうのですが、「やりたくない」も大切な意思表示です。
保育者が少し介入し、子どもたち一人ひとりに「どういうことならやってみたい?」と声をかけて意見を聞いてみました。
すると、「なわとびをしながら走りたい」とか、「まっすぐ走るんじゃなくて、まるく走るほうがいいと思う」とか、既存の方法ではない方法でかけっこをやってみたい、という意見を聞くことができました。
みんなの前ではうまく話せないけれど、実は胸のうちにおもしろいアイディアを秘めている子どもたちがたくさんいることに驚きました。
話し合いで子どもたちの意見を聞く中で、「やりたくない」の背景には、いろいろな「やりたい」が隠れているということに気付くこともできました。
「やりたくない」と言ったとき、大人がすぐにその良し悪しを決めるのではなく、子どもの意見を丁寧に聞くことが大切だということを改めて感じる機会となりました。
社会性が育ち始めているからこそ、ちょっと忖度したり、不本意だけど「いいよ」と言ったりすることも増える年長さん。
運動会の話し合いを通して、
「ほんとうにあなたがしたいことを教えてほしい」という大人やお友だちからのメッセージを受け取り、「本当はこんな気持ちがあるんだよ」と自分の意見も大切にできる気持ち
が育ってくれると嬉しいなと思います。
今年のかけっこの見どころ



練習の段階で3種類のかけっこをそれぞれ体験し、「最初は走るかけっこがよかったけど、ストライダーかけっこにしたい」など、途中で方向転換する子もたくさんいます。
今年のかけっこでは、
①自分でやりたい種目を選び
②選んだ種目を最後まで頑張って取り組むこと
を目標のひとつに設定しています。
私たち保育者としては、「このかけっこだったら力を出し切って頑張れる」と、自分なりに納得のいく形で好きな競技を選んでくれたらいいな、と思っています。
そういった意味でも、今年のかけっこではあえて順位は決めません。勝ち負けという「結果」も大切かもしれませんが、自分たちで選んで決めた種目に、力いっぱいに取り組もうとしている子どもたちの頑張りや、運動会を迎えるまでの練習といった「過程」を大切にしてほしい、と考えています。
保護者の皆様には、お子さんがどの競技を選んだのかにも注目していただきたいですし、子どもたちが最後まで一生懸命取り組む姿を応援していただけると嬉しく思います。
そうはいっても、やはりかけっこは勝敗のある競技です。練習の段階では、思い通りに進めなくて涙する子もいれば、途中で転んでしまい、悔しい気持ちで泣いている子もいました。これも社会性が育ってきているからこそ起こることです。自分と他の子の違いが分かってくるので、「あの子に負けて悔しい!」「速くゴールできる子がうらやましい」と嫉妬心をおぼえるようになるのもこの時期の特徴です。
嫉妬心や羞恥心から、園では積極的に練習しないけれど、おうちに帰って一人で練習したり、「どうやったら速く走れると思う?」「どうやったら上手になるかなあ」と家族にきいていたり、人知れず努力しているお子さんもいるのではないでしょうか。もしご家庭でそういった様子が見られたら、ぜひ一緒にお子さんと運動会に向けての作戦会議を楽しんでいただければ幸いです。
私たち保育者も子どもたちと一緒に準備を楽しみながら当日を迎えたいと思います。
園生活最後の運動会です!当日は子どもたちへの温かな声援をよろしくお願いします!
文責:津田