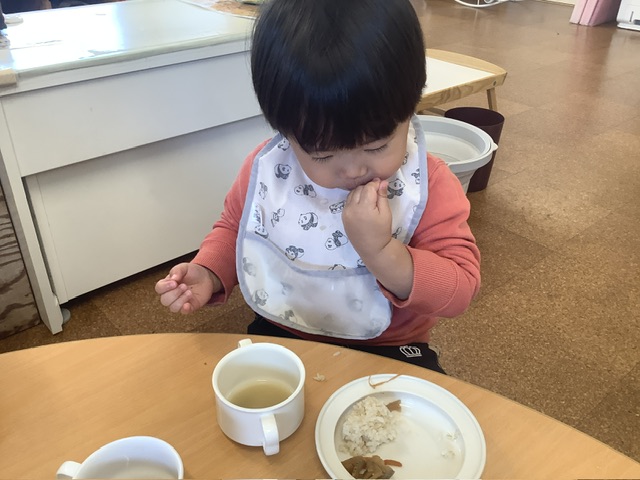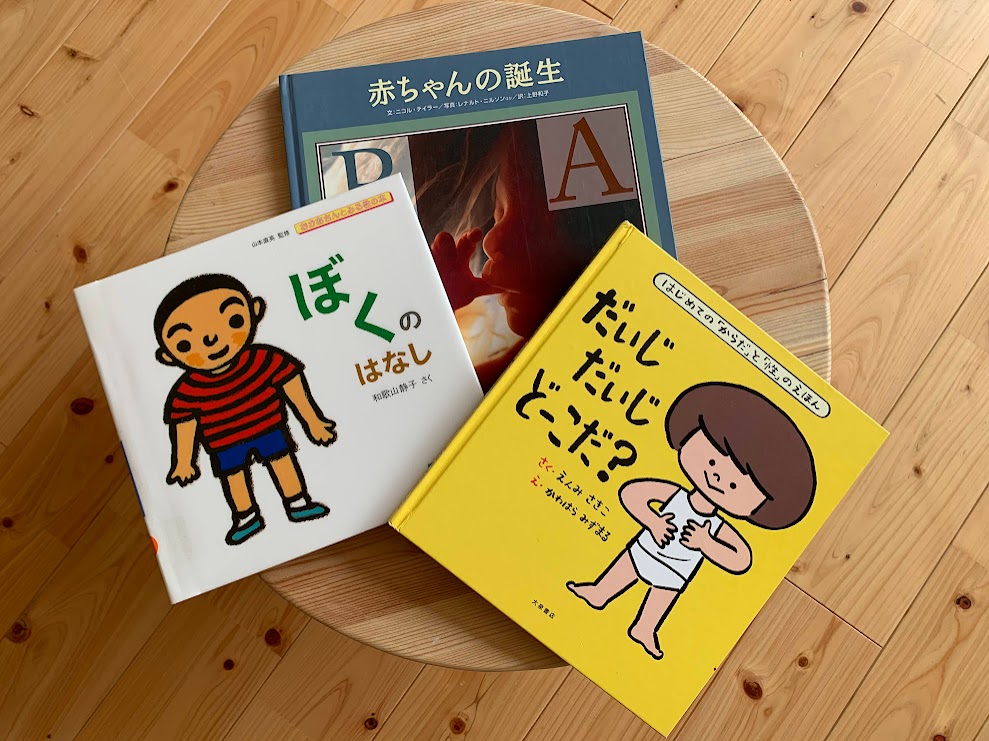お知らせ
2022.09.15
未分類
小麦粉粘土の感触は?(4歳児 こすもす組)

幼児期の子ども達は五感をフルに使って遊び、様々な刺激を受けながら豊かな感性や言葉などを獲得していきます。
その遊びの中でも感触遊びは、第2の脳と言われる『手』で様々な刺激を感じ取ることにより大脳をどんどん刺激することで、脳を活性化させる効果もあるようです。
感触遊びというと水・砂・土・粘土・寒天・氷、等々思い浮かびますが…
今回は小麦粉を使って粘土作りにチャレンジしました。
4人1組でタライを囲むと
早くやりたいなぁ~、小麦粉はまだ?とワクワクしている子、
ちょっと不安そうな表情でドキドキしている子、
様々な感情が、表情や言葉で現れます。

小麦粉が配られると活動スタート!
自分達でそっと袋から小麦粉をタライに入れます。すると、袋の重さを感じたり、袋から出てくる小麦粉の様子を見たりしながら、
「軽い!」「重い!」「わあー出てきた!」
見たり感じたりした事が言葉となって出てきます。
小麦粉ってどんな感触?

「サラサラだね!」
「フワフワしてる!」
「気持ちいいね!」
粉をかき混ぜたり、握りしめたりしながら粉の感触を楽しみ、友達と言葉で感触を確かめ合う声があちこちから聞こえてきます。
活動前に不安そうにしていた子も、友達の楽しそうな姿に誘われ、友達と一緒に笑顔で遊び始めます。
(触ってごらんという大人の声は必要ないのです。友達の遊ぶ姿を近くで見ているうちに、楽しそう自分もやってみたい!という気持ちになれば自然に遊び始めます。)
粉が変化していく感触


粉にペットボトルの水を自分達で入れて粘土にしていきます。
水の入れ方や混ぜ方など、グループのカラーが現れます。一気に全部入れて混ぜるグループや、交代で少しずつ入れて捏ねて、入れて捏ねてを繰り返すグループ!
どのグループも友達と対話しながら小麦粉粘土を作るという目的に向かって協力し合います。
水を足していくうちにだんだん
「手がべちょべちょ〜。」
「ベタベタ。」
「手にくっついて取れな〜い。」
と、不快そうな声のつぶやきが聞こえ始めます。表情まで曇っている子もいます。
一方、この感触を友達とニコニコしながら楽しんで捏ね続けている子もいます。
感じ方はみんなそれぞれで、どちらも大切な感情です。
何かを感じて感情が動く、何かを感じて言葉や表情で表現するなど、何かを感じながら遊ぶ事に意味があるのです。


不快そうにしている子どもの近くに粉を少し足してあげると、
「粉を付けたら手のべちょべちょが取れてきたー!」
とにこやかな声と笑顔が戻ります。それを聞いた友達が、
「こっちにも粉入れてほいし」と訴えます。子ども達の声を聞きながら粉を追加してあげると
「僕も手のベタベタが取れてきた。」
「だんだん粘土になってきたよー!」
友達の声を聞いて、見て真似て、どのグループも粘土作りの意欲が再び高まります。
一緒に遊ぶ友達の存在は、とっても大切な存在です。
友達がいるからこそ遊びが広がり、教え合う事が様々な学びに繋がっていきます。
捏ねられて耳たぶくらいの硬さになると今度は
「気持ちいい〜。」
「楽しい〜。」
の声があちこちから聞こえ始めます。


十五夜前という事もあり、小さくちぎって丸めてお月見団子を作ったり、伸ばして紐のように捏ねたりしながら思い思いに粘土遊びを楽しみます。
自分達で作った粘土は格別です。
心地よい感触と、粘土を作り上げた達成感で、どの子も凄くいい表情でした。
遊び終えた粘土は袋に入れて、足で踏んで感触を楽しんだり、寝そべって体で感触を楽しんだり、座ったしながら、手作り小麦粉粘土の感触を全身で楽しみました。
今回の活動では、粉から粘土になるまでの感触を指先で感じ取り、友達との対話を通してサラサラ・べちょべちょ・などの感触を言葉で確かめ合いながら、友達と協力して遊び込む事ができました。
今後も子ども達の感情が動く遊びをどんどん取り入れていこうと思います。
文責 宮原